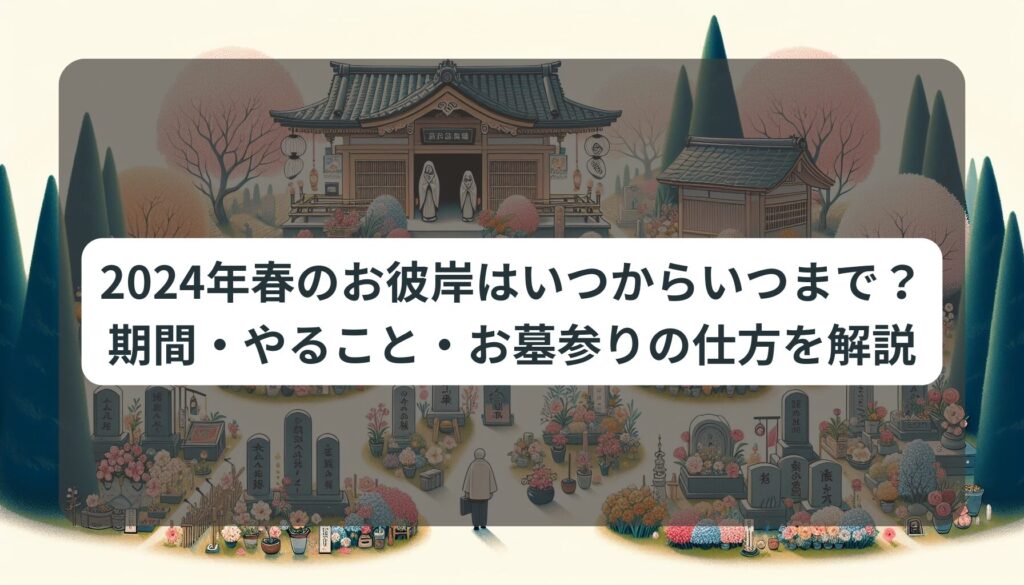法事とは、故人の霊を供養する仏教の儀式です。法事には、法要という別の言葉もありますが、どう違うのでしょうか?また、法事にはいろいろな種類や時期がありますが、それぞれにどんな意味があるのでしょうか?
法事に参列する際には、マナーや服装にも気をつけなければなりません。法事の準備や当日の流れについても、知っておくと安心です。この記事では、法事に関する基本的な知識や注意点を解説します。
法事とは

法事とは、故人の霊を供養する仏教の儀式です。法事は、故人の死後に定期的に行われます。法事の目的は、故人の冥福を祈るとともに、遺族や親族が故人との絆を深めることです。
法事は、故人の命日や忌日に合わせて行われることが多いです。法事には、僧侶が読経や法話を行う法要と、遺族や親族が食事を共にする会食があります。
法事と法要の違いについて
法事と法要は、よく混同される言葉ですが、厳密には違います。法事は、故人の死後に定期的に行われる儀式の総称です。法要は、法事の中で、僧侶が読経や法話を行う部分です。法要は、法事の一部であるとともに、法事以外の場面でも行われることがあります。
例えば、お盆やお彼岸などの節日に、寺院で行われる法要もあります。また、法事は、故人の死後に行われるものですが、法要は、故人の生前に行われることもあります。例えば、病気や災難からの回復を祈る法要や、長寿を祝う法要などがあります。
法事の種類と時期

法事には、故人の死後に行われる回数によって、いろいろな種類があります。一般的には、以下のような法事が行われます。
| 法事の種類 | 時期(亡くなってから) | 説明 |
|---|---|---|
| 初七日 | 7日目 | 故人の死を知らせるとともに、故人の霊を安らかに送るために行われる法事 |
| 四十九日 | 49日目 | 故人の霊が成仏するとされる日。故人の遺志や遺品の処分などもこの日に行われる法事 |
| 百か日 | 100日目 | 故人の霊が冥界に落ち着くとされる日。故人の思い出を語り合うこともある法事 |
| 一周忌 | 1年目 | 故人の命日に合わせて行われる法事。故人の霊が供養されるとともに、遺族や親族の慰めとなる法事 |
| 三回忌 | 2年目 | 故人の霊が輪廻転生するとされる日。故人の功徳や教えを称えることもある法事 |
| 七回忌 | 6年目 | 故人の霊が極楽浄土に行くとされる日。故人の恩や恵みに感謝することもある法事 |
| 十三回忌 | 12年目 | 故人の霊が仏に近づくとされる日。故人の教えや願いを受け継ぐこともある法事 |
| 十七回忌 | 16年目 | 故人の霊が仏になるとされる日。故人の功徳や智慧に学ぶこともある法事 |
| 二十三回忌 | 22年目 | 故人の霊が仏の教えを広めるとされる日。故人の遺徳や影響に感謝することもある法事 |
| 二十七回忌 | 26年目 | 故人の霊が仏の境地に達するとされる日。故人の教えや願いを実践することもある法事 |
| 三十三回忌 | 32年目 | 故人の霊が仏の慈悲に満ちるとされる日。故人の恩や恵みに報いることもある法事 |
| 五十回忌 | 49年目 | 故人の霊が仏の智慧に達するとされる日。故人の功徳や智慧に帰依することもある法事 |
法事の準備

法事を行うには、以下のような準備が必要です。
日程の調整
親族と相談して、法事の日程を決めます。法事の種類や時期によって、日程が決まっている場合もありますが、参列者の都合も考慮しましょう。
会場の予約
自宅で行う場合は問題ありませんが、寺院や斎場で行う場合は予約が必要です。法事の規模や予算に応じて、会場を選びましょう。
僧侶への依頼
法要をお願いする僧侶に連絡し、日程や読経の内容などを確認します。僧侶の選び方は、故人や遺族の信仰や縁によって異なりますが、一般的には、故人が所属していた寺院や宗派の僧侶に依頼することが多いです。
参列者への連絡
親族や友人など、法事に参列してもらう人に連絡をします。連絡の方法は、電話やメール、はがきなどがありますが、法事の日程や場所、服装などの必要な情報を伝えましょう。
供物の準備
法事に必要な供物(お供え物)を用意します。供物には、故人の好きだったものや、仏教の教えに沿ったものが選ばれます。一般的には、花や果物、お菓子、お線香、お金などが供物として用意されます。
服装の準備
法事にふさわしい服装を用意します。法事の服装は、黒や紺などの落ち着いた色の喪服が基本です。ただし、法事の種類や時期によって、服装の色や柄に違いがあります。
例えば、初七日や四十九日などの法事では、白や灰色などの白喪服が着用されることがあります。また、一周忌や三回忌などの法事では、紫や茶色などの色喪服が着用されることがあります。服装の選び方は、故人や遺族の意向に従いましょう。
法事当日の流れ

法事当日の流れは、以下のようになります。
開式
僧侶による読経が始まります。読経とは、仏教の経典を読み上げることです。読経には、故人の霊を慰めるとともに、仏の教えを聞くという意味があります。読経の間は、静かに聞き入りましょう。
焼香
参列者が順番に焼香を行います。焼香とは、お線香を火につけて、その煙を故人の霊に捧げることです。焼香には、故人に対する敬意や感謝の気持ちを表すという意味があります。焼香の仕方は、以下のようになります。
- 僧侶の合図で、参列者は一列に並びます。
- 最初に施主が、お線香の入った容器に手を合わせて礼をします。
- 施主は、お線香を一本取り出して、火につけます。
- 施主は、お線香を火につけたまま、故人の遺影や位牌に向かって、二礼二拍手一礼をします。
- 施主は、お線香を火につけたまま、お線香の入った容器に戻して、手を合わせて礼をします。
- 施主の後に、親族や友人などが同じように焼香をします。
法話
僧侶による法話が行われます。法話とは、仏教の教えや故人の人生について語ることです。法話には、故人の霊を導くとともに、参列者の心を慰めるという意味があります。法話の間は、静かに聞き入りましょう。
食事
会食が行われます。会食とは、参列者が一緒に食事をすることです。会食には、故人の霊に食事を供えるとともに、参列者の交流を深めるという意味があります。会食の内容は、故人の好きだったものや、仏教の教えに沿ったものが選ばれます。会食の間は、故人の思い出を語り合ったり、感謝の言葉を伝えたりしましょう。
閉式
僧侶による読経で法事が終わります。閉式の読経には、故人の霊を安らかに送るとともに、参列者の心を清めるという意味があります。読経の後に、僧侶に対してお布施を渡します。お布施とは、僧侶に対する感謝の気持ちを表すお金です。お布施の金額は、法事の規模や予算に応じて決めます。
法事後の対応
法事が終わった後には、以下のような対応が必要です。
参列者にお礼状を送ります。お礼状には、法事への参列やお供え物などに対する感謝の言葉を書きます。お礼状の送付は、法事の後に早めに行うのがマナーです。
法事の後も、故人の冥福を祈り続けることが大切です。供養の方法は、故人の遺影や位牌に手を合わせたり、お線香やお花を供えたり、お墓参りをしたりすることです。供養の頻度は、故人や遺族の信仰や習慣によって異なりますが、一般的には、故人の命日や忌日に行うことが多いです。
法事のマナーと服装

法事に参列する際には、以下のようなマナーや服装に気をつけましょう。
- 時間厳守
-
法事は、故人に対する最大の敬意です。法事の開始時間に遅れないように、余裕を持って会場に向かいましょう。もし遅れそうな場合は、事前に施主に連絡しましょう。
- 落ち着いた服装
-
法事は、故人の霊を供養する厳粛な儀式です。法事にふさわしい服装を着ましょう。服装の色や柄は、黒や紺などの落ち着いた色が基本です。ただし、法事の種類や時期によって、服装の色や柄に違いがあります。服装の選び方は、故人や遺族の意向に従いましょう。
- 飲食の節度
-
法事の会食は、故人の霊に食事を供えるとともに、参列者の交流を深める場です。飲食の際には、故人に対する敬意や感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。飲食の量や種類は、故人の好きだったものや、仏教の教えに沿ったものが選ばれます。飲食の際には、過度な飲酒や大声での会話などは控えましょう。
- 携帯電話の電源オフ
-
法事は、故人に対する最大の敬意です。法事の間は、携帯電話の電源を切るか、マナーモードにしましょう。携帯電話の着信音や振動が、法事の雰囲気を乱すことがあります。もし緊急の連絡が必要な場合は、法事の合間に会場の外で対応しましょう。
法事に関するよくある質問
法事に関して、よくある質問とその回答を以下に紹介します。
法事は何回忌まで行うべきですか?
法事を行う回数に決まりはありません。一般的には、一周忌、三回忌、七回忌などが行われることが多いです。しかし、故人や遺族の信仰や習慣によって、法事を行う回数や種類は異なります。
法事を行うことは、故人の霊を供養するとともに、遺族や親族が故人との絆を深めることです。法事を行うかどうかは、故人や遺族の意向に従いましょう。
法事の費用は誰が負担するべきですか?
法事の費用は、施主(喪主)が負担するのが一般的です。法事の費用には、僧侶へのお布施や会場の使用料、食事の代金などが含まれます。法事の費用は、法事の規模や予算に応じて決めます。法事の費用を抑える方法としては、以下のようなものがあります。
- 自宅で法事を行う
- 寺院や斎場の割引プランを利用する
- 食事の内容や量を調整する
- 参列者からの香典を受け取る
法事に参列できない場合はどうすれば良いですか?
法事に参列できない場合は、事前に施主に連絡し、お詫びの言葉を伝えましょう。法事に参列できない理由は、仕事や病気など様々ですが、施主に対する配慮として、連絡は早めに行うのがマナーです。法事に参列できない場合でも、故人に対する敬意や感謝の気持ちを表す方法としては、以下のようなものがあります。
- 香典や供物を送る
- 法事の日にお線香やお花を供える
- 法事の後に施主にお悔やみの言葉を伝える
- 法事の後にお礼状を送る
まとめ
法事とは、故人の霊を供養する仏教の儀式です。法事には、法要と会食があります。法事には、いろいろな種類や時期があります。法事を行うには、日程の調整や会場の予約、僧侶への依頼などの準備が必要です。法事に参列する際には、時間厳守や落ち着いた服装、飲食の節度などのマナーに気をつけましょう。
法事に関して、よくある質問とその回答も紹介しました。法事は、故人に対する最大の敬意です。法事を通して、故人の霊を慰めるとともに、遺族や親族との絆を深めましょう。